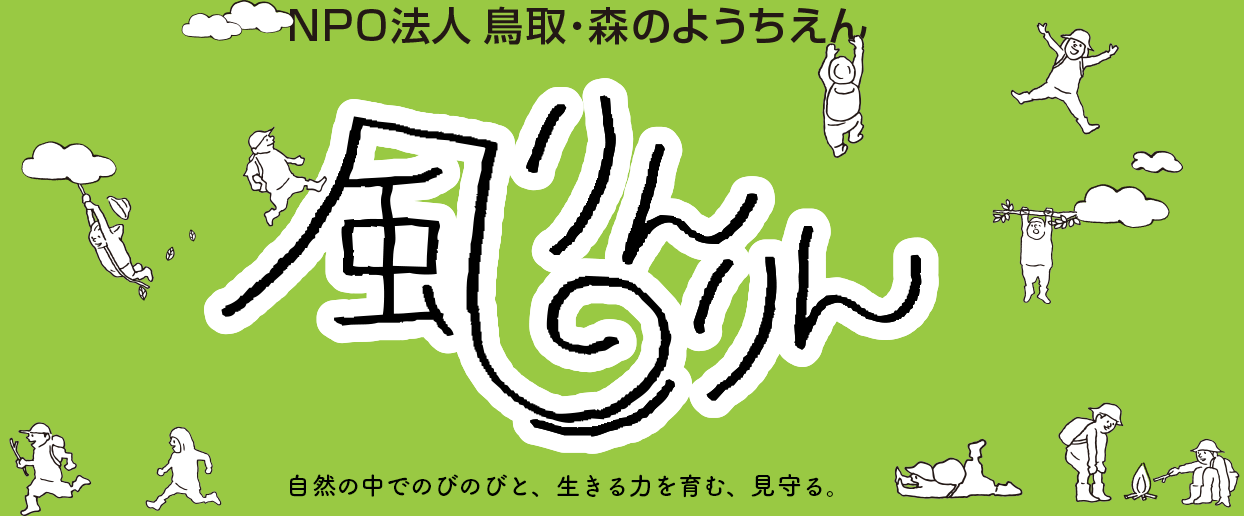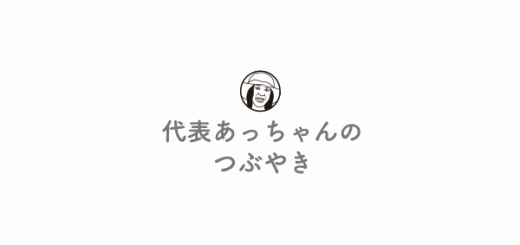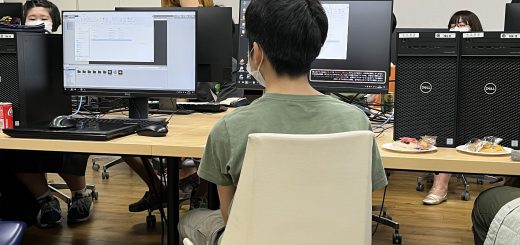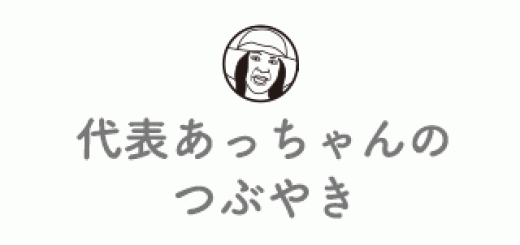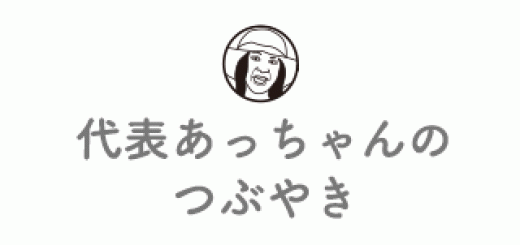ルールはあたしたちおれたちが決める ~仕事しない人は食べたらいけんでー~
なんともすごみのある写真から入りました笑
別に喧嘩をうってるわけでもなく、週1の野外」クッキングを終えて出来上がったご飯をおいしそうに(?笑)食しているところです。
この写真のもつ力ってすごいなー
さて話は戻り、毎年6月には「ういてまて」講習を行います。海で流されてしまったとき、必死に泳いて助けを求めるではなく、ただ上を向いて「ういてまてー」と浮かんでいよう、そしたら助けにきてくれるから。というものです。浮いていれば必ず助けてくれる。
風りんりんが開園した2014年くらいに、当時消防士の「中村昭」さんにスタッフが講習をしてもらいました。(中村昭さんのインタビュー記事はHPに記載されています)「今まで水難にあった人の救助に向かったが救助できたのは1名のみ。浮いてさえいれば助けられた。」と辛い話を聞きました。「水難は1秒で起こる。だから子どものすぐそばにいなければいけない。何かあってから手を伸ばすのでは遅い。」「とにかく浮いていれさえすれば助けられる。水に入るときはライフジャケットを必須にしてほしい。」
すぐに各家庭にお願いしてライフジャケットを購入してもらいました。今ほどライフジャケットが知られていない時代です。子どもが自分で装着できるよう親子で練習し、現場でできない子がいれば手伝ってあげ、その重要性を理解している子どもたちは、ライフジャケットを忘れたら水に入らないと決めています。
久々に「風りんりんの森のお約束」を書きます。
1, お茶を飲む
2, 帽子をかぶる
3, 蜂や蛇がいたら大声を出さずにそーっと後ろに逃げる
4, 草が長く生えているところは蛇がいるかもしれないから近づかない
5, 森で食べたい草やキノコなどがあったら大人に聞いてから食べる
6, 大人が見えないところに行かない。行きたいときは大人を連れていく。
11年間変わらず継承されてきたルールは子どもたちを守り、子どもたちが新たに追加したものも継承されています。
つまり
「自分で必要と感じるルール、自分で作ったルール」は守る。
逆に言うと人が勝手に決めたことは守らない、必要と思わなければ守らない。
これは大人も一緒ですね。
方法やヒントや体験が溢れる環境つくりしながら、子どもがどこへ向かうのか、自分の身を自分で守れるようになるよう、私たちスタッフも頑張ります。
子どもがもつ「大人の何倍も強く持っている危険察知能力」を大切にしながら。
最後にクッキングのときのルール名セリフ
仕事しない人は食べたらいけんでー